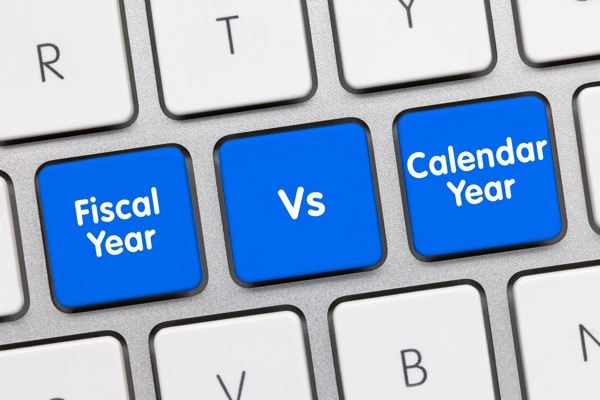
将来の相続税対策として、「暦年課税」による生前贈与を検討している人も多いのではないでしょうか。
暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に一人の人が贈与された財産合計額のうち、110万円以下の贈与は非課税になる制度です。
相続税対策として有効な手段ですが、注意点もあり理解したうえで利用することが大切です。
この記事では暦年課税のメリットと注意点、贈与税の計算方法と申告方法、比較されることの多い「相続時精算課税制度」との違いについて解説します。
- 暦年課税は、年間110万円以下の贈与が非課税となる制度で、相続税対策に利用される。
- 暦年課税は贈与回数に制限がなく、相続人以外への贈与も可能。
- 多額の贈与には暦年課税は不向きで、贈与額によっては高い税率が適用される。
目次
暦年課税とは

暦年課税とは、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与財産が110万円までのとき、非課税になる課税制度です。
注意したいのは、一人が「受け取る額」の上限が110万円であるということです。
たとえば、「祖父母が孫にそれぞれ110万円ずつ贈与すれば、合計220万円まで非課税」という勘違いをする人がいますが誤りです。
この場合は110万円を超えた分(110万円)に贈与税がかかります。
この制度を活用することで、生前に計画的に財産を子や孫、それ以外の人へ移転できます。
財産を減らすことができるので、自分の死後を見越して相続税を節税できるよう、利用する人が多い制度です。
なお、贈与を受ける人(もらう人)を「受贈者」、財産を与える人を「贈与者」といいます。
暦年課税の仕組み
贈与税は、贈与がおこなわれた際に毎年の「贈与額を超える部分(基礎控除を引いた額)」に課税をおこなう制度です。
この制度では、毎年の贈与額に対して110万円の「基礎控除」が適用され、110万円を引いた超過分に対して課税されます。
もし贈与額が基礎控除の枠内(110万円以下の額)であれば、贈与税は課税されず、申告する必要もありません。
また、これは毎年計算し直されるため、何年も贈与して結果的に贈与した合計額が大きく増えても問題ありません。
つまり、「相続税対策としての暦年課税の活用」とは、贈与者が贈与税の仕組みを利用して、「毎年コツコツと110万円以下を受贈者に渡し、財産を移動させていくことで、相続税のかかる財産を自分が生きているうちに減らしていく」やり方を指しています。
暦年課税制度は利用対象者に制限はないため、贈与者は誰にでも贈与できます。
相続人である配偶者や子どもはもちろん、相続人ではない人(子の配偶者や孫なども含む)への贈与でも問題なく、控除枠内であれば課税されないことも変わりません。
さらに、回数にも制限がありません。
暦年課税を使った贈与税の計算方法

暦年課税における贈与税は、毎年の贈与額から110万円の基礎控除を差し引いた金額に対して贈与税率を適用して計算します。
基礎控除を超える部分が課税対象となり、その金額に対して贈与税が計算されます。
具体的には、贈与税率(10%〜55%)を超過分に適用し、課税される金額を算出します。
基本的な贈与税の計算方法は以下のとおりです。
1.年間で贈与した合計金額から基礎控除額(110万円)を差し引く。
2.差引額に対して累進課税を適用して贈与税を計算する。
(例):1年間に孫に200万円を贈与した場合の贈与税の計算
200万円 - 110万円 = 90万円
90万円に対して該当の累進課税税率(200万円以下なので10%)を適用、贈与税を計算
90万円 × 10% = 9万円
3.控除額を引く。
※上記の例では基礎控除を引いた金額が200万円以下の贈与なので控除無し。この控除は基礎控除とは別。下記の表参照。
累進課税とは、贈与された額の範囲によって税率が変わるものです。
税率は、贈与額によって決まっています。
速算表(一般贈与財産用)】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【速算表(特例贈与財産用)】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
関連記事
贈与税の基礎控除額はいくら?計算方法と利用する場合の注意点を解説
暦年課税のメリット
基礎控除額より多い額の贈与を受けた場合は、贈与税を支払うことになります。
その場合、暦年課税と相続時精算課税、どちらかで支払います。
ここでは暦年課税を使う場合のメリットを解説します。
暦年課税を利用して贈与をおこなうメリットは以下のとおりです。
1.年間110万円までは基礎控除枠内のため課税されない
従来は精算時課税制度と比較してメリットとされた点です。
贈与税の基礎控除は110万円までのため、110万円以下の額を毎年贈与している場合、課税されません。
ただし、2024年1月1日以降(経過措置あり)は、生前贈与加算が贈与人の死亡3年前~7年前までとなります。
これに該当した贈与財産は110万円以下の基礎控除額以下でも相続財産として扱われるため、贈与税と相続税を計算し比較する場合は注意が必要です(生前贈与加算は相続人が対象)。
2.何度でも贈与が可能
暦年贈与に回数制限はなく、何回贈与しても問題はありません。
ただし、精算時課税制度も回数制限はないため、比較して大きなメリットというわけではありません。
ただ、相続が1回きりと考えると、生前に自分の資産を渡して資産額をコントロールできる贈与の制度を、毎年非課税で使える暦年課税制度はメリットといえるでしょう。
3.受贈者の税負担を軽減できる
暦年課税では、年間110万円までの贈与が非課税となるため、贈与額を調整することで受贈者の税負担を軽減できます。
一度に多額の贈与をおこなうと高い税率が適用されますが、毎年少額ずつ贈与することで累進税率の影響を抑えられます。
特に、相続税率が高くなる高額資産をお持ちの方にとっては、有効な節税対策となります。
ただし、毎年同じ金額を贈与する場合、定期贈与とみなされるリスクがあるため、贈与契約書を作成し、個別の贈与として証拠を残すことが重要です。
4.資産の早期移転ができる
暦年課税を利用することで、計画的に資産を早期移転できます。
特に、高齢になってから一度に大きな財産を相続させるよりも、生前に少しずつ財産を移転することで、受贈者が資産を活用しやすくなります。
たとえば、子や孫の教育資金や住宅購入資金として活用すれば、資産の有効活用にもつながります。
また、相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となりますが、それ以前の贈与は対象外となるため、早めに贈与を開始することで相続対策としても有効に機能します。
5.相続税の節税効果が期待できる
相続税の課税対象となる財産を減らすために、暦年課税を活用した生前贈与が有効です。
年間110万円以内の贈与を継続的におこなえば、相続財産の減少につながり、最終的な相続税負担を軽減できます。
特に、相続税の基礎控除額を超える財産を持つ場合、計画的に贈与することで課税対象額を減らせるため、相続税の節税効果が期待できます。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象となるため、長期間にわたる計画的な贈与が重要です。
関連記事
家族間贈与とは?家族の間で財産を贈るメリットや非課税となる特例を解説
暦年課税のデメリット
続いては暦年課税のデメリットを解説します。
1.多額の贈与には向いていない
贈与を非課税でおこなうため暦年課税を使う場合、非課税枠は毎年110万円以下になります。
非課税枠を超えた金額を贈与した場合は、受贈者が金額に応じた贈与税を納めます。
この税率は、相続税と比較すると同じ金額でもかなり高いです。
たとえば、贈与額が1,000万円を超えると40%以上になってしまいます(相続税では、1,000万円超では15%がスタートの税率です)。
一方、相続時精算課税制度の場合、税率は一律20%です。
また相続が発生した際には、贈与時の時価が適用となります。
暦年課税は、非課税枠を超えた場合に対する税率は精算時課税よりも高いため多額の贈与には向いていないといえます。
大きな金額を一度に贈与したい人や財産が非常に多い人、現在の時価よりも相続時に時価が上がっていそうな人は、暦年課税による贈与は向いていないかもしれません。
2.暦年課税をおこなうと、その都度申告が必要
暦年課税をおこない、その金額が基礎控除額の110万円を超えた金額がある場合は、受贈者(もらった人)は毎年申告が必要です。
そのため贈与者(お金を渡す人)が暦年課税を使って資産の移動を考えるならば、受贈者に負担をかけないよう、110万円以下の金額をコツコツ贈与する方が望ましいでしょう。
3.毎年の贈与が「定期贈与」とみなされるリスクがある
暦年課税を利用して毎年同じ金額を贈与している場合、それが「定期贈与」とみなされるリスクがあります。
定期贈与とは、たとえば「毎年110万円を10年間贈与する」といった契約があると判断され、一括贈与とみなされるケースです。
この場合、全体の金額が贈与税の累進税率で課税されるため、結果的に高額な税負担が生じます。
これを防ぐには、贈与契約書を作成し、毎年異なる金額を贈与するなど、個別の贈与として認識される工夫が必要です。
4.管理や手続きが手間になる
暦年課税を活用した生前贈与は、計画的におこなうことで節税効果が期待できますが、その一方で管理や手続きの手間が増えます。
贈与を証明するために、毎年贈与契約書を作成し、銀行振込などの記録を残すことが重要です。
また、110万円を超える贈与をおこなった場合は、贈与税の申告が必要となります。
さらに、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、長期的な計画を立てる必要があります。
こうした管理を怠ると、税務調査で指摘を受ける可能性があるため、注意が必要です。
関連記事
家族間の贈与税はどうなる?税金がかかるケースとかからないケース
相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、贈与時に一度まとめて課税し、将来の相続時に精算する制度です。
60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への贈与が対象で、累計2,500万円まで非課税で贈与できます。
2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかりますが、最終的に相続時に相続税として再計算され、払いすぎた贈与税は還付されます。
この制度を利用すると、早期にまとまった財産を移転できますが、一度選択すると暦年課税に戻せない点に注意が必要です。
ここでは相続時精算課税制度について、暦年課税と比較して解説します。
1.相続時精算課税を選択すると暦年課税には二度と戻せない
相続時精算課税制度を一度選択すると、その選択は撤回できず、贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。
この制度は贈与者と受贈者の組み合わせごとに適用されるため、たとえば父から子への贈与で選択した場合、その父と子の間では二度と暦年課税に戻すことはできません。
このため、将来の税制改正や家族の資産状況の変化に対応できなくなるリスクがあります。
また、贈与者が亡くなるまでの期間が長い場合、制度選択時には想定していなかった不利益が生じる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
2.高額な贈与が可能
相続時精算課税制度では、2,500万円までの特別控除枠があるため、一度に高額な贈与が可能です。
暦年課税では年間110万円を超える部分に10%~55%の累進税率で課税されます。
相続時精算課税制度では特別控除枠を超える部分に一律20%の税率が適用されるため、高額資産の移転に有利な場合があります。
特に不動産や事業承継など、分割が難しい高額資産の生前贈与に適しています。
また、資産価値の上昇が見込まれる資産を早期に移転することで、将来の相続税評価額の増加を抑制する効果も期待できます。
3.複雑な制度のため専門家に相談したほうがリスクは少ない
相続時精算課税制度は、生前贈与と相続を一体的に捉える複雑な仕組みです。
贈与時と相続時の両方の税金計算に影響するため、長期的な視点での税務計画が必要となります。
また、贈与財産の種類や評価方法、受贈者の将来的な資産状況、相続時の税率変動リスクなど、多角的な検討が求められます。
これらの複雑な要素を適切に分析するには、税理士などの専門家のアドバイスが不可欠です。
専門家に相談することで、自分の家族構成や資産状況に合わせた最適な選択ができ、将来的な税負担の誤算やトラブルを回避できる可能性が高まります。
暦年課税と相続時精算課税の違い
暦年課税制度と相続時精算課税制度の違いをまとめると、以下のようになります。
【暦年課税制度と相続時精算課税制度の違い】
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 制度の概要 | 1年間(1月1日〜12月31日)の贈与ごとに贈与税を計算・納付する制度 | 生前贈与と相続を一体化して課税する制度 |
| 選択・適用 | 特に手続きなく適用される(デフォルト) | 贈与者と受贈者双方の合意と税務署への届出が必要 |
| 適用対象者 | 制限なし | 贈与者:60歳以上の親(または祖父母) 受贈者:18歳以上の子・孫(直系卑属) |
| 非課税枠 | 年間110万円までの基礎控除あり | 累計2,500万円までの特別控除あり |
| 税率 | 超過累進税率(10%〜55%) | 特別控除超過分は一律20% |
| 相続時の取扱い | 贈与から3年以内の贈与分のみ相続財産に加算 | 贈与時期に関係なく、贈与財産はすべて相続財産に加算 |
| 贈与税の計算 | 贈与のたびに計算し、毎年申告・納税 | 2,500万円超過分のみ一律20%課税で相続時に相続税から控除 |
| 適用期間 | 毎年の贈与ごとに完結 | 一度選択すると原則撤回不可で相続時まで継続適用 |
| メリット | ・毎年110万円まで非課税 ・相続時に加算されるのは3年以内の贈与のみ |
・2,500万円までの一括贈与が非課税 ・税率が一律20% |
| デメリット | ・高額贈与の場合、累進課税で税率が高くなる ・年110万円を超える贈与は課税 |
・一度選択すると撤回できない ・相続時に贈与財産すべてが加算される |
暦年課税を利用する場合の注意点4つ

暦年課税を利用して贈与をおこなう場合の注意点について解説します。
1.贈与後の通帳管理は受贈者に任せなければならない
暦年課税を利用する場合、贈与する資金を入れている通帳管理は受贈者に任せなければなりません。
たとえば、祖父が孫の名前の通帳に毎年100万円振り込んでいたけれど、その通帳の存在を孫は知らなかった場合、名義預金とみなされ贈与と認められない可能性が高くなります。
2.計画的贈与とみなされないよう注意する
毎年「定期的な」「同一金額の」贈与をおこなっていると税務署から計画的贈与とみなされ、贈与者が死亡した後、課税されるおそれがあります。
暦年課税では毎年贈与をおこなう場合、定期的な一定金額の贈与は避けるべきです。
3.贈与をおこなっている証拠を残さなければならない
暦年課税を利用する場合、贈与をおこなっていることの内容を証拠として、長期間残すことが重要です。
不定期かつ金額が異なる贈与をおこなうことが望ましいですが、この証拠を残すためには、現金手渡しではなく口座への振り込みを利用し、受贈者はその通帳をきちんと保管することが大切です。
4.生前贈与は最大7年相続財産に加算される
生前贈与をおこなう際は、受贈者と制度の変更点を共有し、慎重に進める必要があります。
2024年の改正により、相続開始前の加算対象期間が最大7年に延長されるため、長期間にわたる贈与が相続財産に加算される可能性があります。
たとえば、毎年110万円以下の贈与を7年間続けると、合計700万円が相続財産に含まれ、相続税の負担が増えるおそれがあります。
ただし、この加算は相続人への贈与に適用されるため、子の配偶者や孫などの法定相続人以外には通常適用されません。
ただし、孫を養子にした場合や、生命保険の受取人に指定した場合は、みなし相続人として加算対象になります。
さらに、適切に贈与をおこなっていないと税務署に計画的贈与と判断され、後から課税される可能性もあります。
暦年課税を活用する際は、ルールを正しく理解し、不安があれば専門家に相談することが重要です。
関連記事
贈与税がかからない方法ってある?贈与税が非課税になる特例の内容を徹底解説
暦年課税がおすすめな人
上記のメリット・デメリットや注意点、相続時精算課税との違いから、贈与をおこなう場合に暦年課税の活用が向いている人をまとめると、以下のようになります。
1.相続税を節税したい人
相続税の節税を考えており、かつ、贈与税もできれば発生させずに済ませたい人(贈与税における、毎年110万円以下の基礎控除枠を利用したい人)は、暦年課税の基礎控除枠内での贈与をおこなうことで、受贈者の納税負担を増やすことなく相続税を節税できます。
2.贈与対象者(受贈者)が多い人
暦年課税では非課税で贈与をおこなおうとすると、少ない金額をこまめに渡すことになります。
資産が多く、できるだけ相続発生前に減らしておきたい場合は、贈与対象者が多い人が適しているといえるでしょう。
なお、誰が受贈者になっても問題ありません。
3.長期的にコツコツ資産移動するのが苦にならない人
暦年課税を非課税でおこなう場合、毎年110万円以下の資産移動を長期的におこなうことになります。
また「毎年毎月同一日に同一金額」などをしてしまうと、「計画的贈与」とみなされ追徴課税が発生するおそれがあります。
そのため、日付や金額を変え、誰にいつどれくらい贈与したか、贈与契約書などを作成しつつ記録をとり、こまめに作業することが苦にならない人に適しているといえるでしょう。
4.孫(法定相続人やみなし相続人ではない)に資産を非課税で渡したい人
贈与者が祖父母の場合、孫は法定相続人ではないため、贈与者が死亡したときも相続人にはなりません。
そのため3年以内加算の対象にもなりません。
孫に生きているうちに財産を渡しておきたい人には適した方法といえます。
まとめ

本記事では贈与税における暦年課税とはどのような制度・仕組みなのかを解説しました。
また、暦年課税のメリット・デメリットや精算時課税の違いなども解説しました。
暦年課税は贈与に対する課税制度の一つであり、110万円の基礎控除が適用されるため、相続税対策などに活用されています。
しかし細かい注意点も多く、制度の仕組みや注意点を理解したうえで利用することが大切です。
暦年課税と精算時課税、どちらの制度を選ぶかは個々の状況によって異なります。
できれば贈与税に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
関連記事
贈与税はいくらから発生する?贈与税の計算の仕組みと非課税になる特例も紹介





